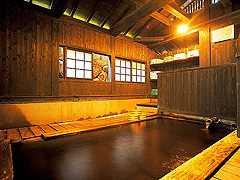日田市の北部に位置する「小鹿田焼の里(おんたやきのさと)」は、1705年に柳瀬三右衛門により開窯されました。窯元が谷川の水を利用した唐臼(からうす)で土を砕き、薪を使う登り窯で焼くという昔ながらの技法で作られる素朴な焼き物の里として知られています。今でも日用的に使われる什器として親しまれています。
昭和29年に英国の陶芸家バーナード・リーチ氏が訪れた後に全国的に有名になり、平成7年には国の重要無形文化財に指定されました。
また、陶土を挽く唐臼の音は「日本の音風景100選」、地区全体は重要文化的景観として選定されています。
(2024.2)




| 住所 | 大分県日田市源栄町皿山 |
| お問い合わせ先 | 小鹿田焼陶芸館 TEL:0973-29-2020 |
| 休日情報 | 不定休 |
| 駐車場 | あり |
| アクセス | 大分自動車道日田ICから車で約30分 |
| HP | https://www.oidehita.com/archives/304 |
“唐臼”の音が響く「皿山地区」
小鹿田焼と皿山地区

小鹿田焼が生まれたのは今から300年近く前、1705(宝栄2)年のことでした。日田郡大鶴村の黒木十兵衛が、福岡県朝倉郡小石原村の陶工・柳瀬三右衛門を招いたことに始まります。三右衛門は十兵衛とともに窯業に適した地を探し、小鹿田に李朝系の登窯を築いたのです。この地が選ばれた決め手は、登窯の築窯に適した斜面があったこと、また豊富な陶土や薪、そして水力の利用に便利な自然環境であったからと考えられています。
300年前の開窯当時のままに、伝統技法を守り続ける「小鹿田焼」。素朴で温もり溢れる「小鹿田焼」は、“暮らし”のための器。
「小鹿田焼」は、民衆の暮らしのための日用雑器“民陶(民藝陶器)”です。
“官窯”とは異なり、華麗さや繊細さはありませんが、質実で柔らか、素朴で温かみがあります。「飛び鉋(かんな)」や「刷毛」「櫛」などの道具を用いて付けられた幾何学的な紋様や、「打ち掛け」「流し掛け」された釉薬が生み出す柔らかみや温もりは、素朴ながらも時代に負けない堅牢さがあります。

(都市整備課写真・加工後)-768x384.jpg)